「C」
窓の外。4月の黄色い陽光の下、桜の花びらが舞っている。
風に乗って踊り、輪を描いて回る桃色の妖精を引き立てるかのように、蝶がヒラヒラと飛んでいた。
次々に咲き始めた花壇の花を眺めながら、どの花の蜜を吸おうか迷っているのだろうか。
1匹の蝶が花壇にある赤い花に降りる。
蝶は花に止まったまま翅をゆっくりと開いたり閉じたり…その様子は、まるで蝶が蜜の味を満喫しているかのようにも見えた。
桃色の桜、黄色や白色の蝶、赤色や橙色の花、緑色の草。
窓の外にあるのは、誰が何と言おうと暖かな春の情景だった。
そんな情景を見て、今の私が思う事はただひとつ。
――眠い。
暖かな4月の陽光も窓の外で踊る桜の花びらも咲き誇る花々も萌える草の緑も、私にとっては自分を心地よい眠りに誘う催眠術でしかなかった。
「ふわぁ…ぁふ」
情けないくらいの大きな欠伸が出てしまう。
そこ、はしたないと言うなかれ。
始業式が終わり、明日から再び学校生活が始まるのだ。
今のうちにこうやって鋭気を養っておかなければ、こうやって学校に来る事すら止めてしまうかも知れない。
……さすがにそれは冗談だけど。
「ふぁ……」
あらら、油断していたらまた欠伸が…。
2度目の欠伸はさすがに恥ずかしいので、一応は手で口を隠しておく。
やれやれ…どうやら今日の睡魔は一段と強力らしい。
私の精神はことごとく睡魔に侵食されていき、自我は既に3%も残っていない。
自我が必死に睡魔を押し返そうとしているのが分かる。
だが、それは無駄だ。
何故なら、私の体が素直に睡魔を受け入れているから。
人類が抗う事の出来ない睡魔をもたらす暖かな陽光が、容赦なく私を照らし続けるこの窓際の席が半分悪い。
残り半分は眠気を助長するような暖色のみで彩られる窓の外の情景が悪い。
うん、私は悪くない。悪くない。
……よし、自己正当化完了。
「ふわあぁ……」
と同時に、またまた口から漏れる欠伸。
むむ。これは、休憩時間である今の間に眠っておいた方が良さそうだ。
ホームルームまで眠っていてはシャレにならない。
まあ…始業式当日のホームルームなんて、一緒に渡されるプリントを見れば事足りるような連絡事項しか言わないだろうけど。
私は時計に目を向ける。
ホームルームが始まるまではあと5分。
…………。
……5分でどうやって眠れってのよ。
私は誰へともなく毒づく。
どこぞの漫画にある時間の流れが遅くなる修業部屋じゃあるまいし、5分で十分な睡眠時間などとれるわけが無い。
逆にそんな短い睡眠時間じゃ、かえって眠くなってしまうこと請け合いだ。
……仕方がないか。
「う〜ん…っ」
私は欠伸を噛み殺しながら両手を頭の上で組み、大きく伸びをした。
肩の骨がパキパキッと小気味良い音を立てる。
眠る時間がないと分かれば、今のうちに出来るだけ睡魔を吹き飛ばすしかない。
睡魔ちゃん、短い付き合いだったね。
勝負とは常に非情なのだ。
何の勝負かは知らないけど。
私は頭の上で組んだ両手を離し、そのまま肩を交互にぐるぐると回す。
「うわ、女の子がそんなはしたない事をしちゃダメだよー」
私の後ろから、間延びした女の子の声が聞こえた。
私は上げた腕を下ろす。
「女の子が…っていうのは決めつけだよ。私は女の子らしい“おしとやかさ”っていうのは性に合わないの」
そして、振り向きざまに一言。
後ろに誰が居るかは分かっている。
「…そうかなー。理沙ちゃん、可愛いのにー…」
そこには、私が予想した通りの子が眉をハの字にして首を傾げていた。
肩まで伸ばしたふわふわの柔らかそうな髪の毛と、それを引き立てるように髪につけられた小さな赤いリボン。
物静かそうな小さな口と、おだやかさと優しさを兼ね備えたような僅かに垂れた目。
フリフリのドレスなど着せたなら、お人形として売られていてもおかしくないその外見は、彼女が“可愛い”と言った私なんかよりも数倍可愛らしい。
「……おだてたって何もでないわよ? それよりゆーりん、何か用なの?」
目の前のお人形…もとい、“ゆーりん”こと野原由利(のはらゆり)に、私は尋ねる。
「あれー…? 私が用事があるって、何で分かったのー?」
ゆーりんは十分に噛んだガムをビローンと引き伸ばしたような声で不思議そうに問い返した。
別に用事があると分かって言ったわけじゃないんだけど。
話しかけてきたからどうしたのかなー、程度で。
「まあ、女の勘ってヤツかな」
答えようがないので適当に答えておく。
「そうなんだー、女の勘ってすごいねー」
やけに感心しているゆーりん。
いつも思うけど、ゆーりんってちょっとだけ浮世離れしてると言うか…ワンテンポ遅れているような、そんな感じがする。
「…それでさ、用事ってなに?」
私は脱線しかけた話を再び線路に乗せた。
このままゆーりんを放っておくと、用事とやらを聞く前にホームルームが始まってしまいそうだ。
「あ、そうだよー」
ゆーりんはポンと両手を合わせる。
「すっかり忘れてたよー」
……話しかけた理由を忘れないでよ。
「あのね、理沙ちゃんを呼んでる人が廊下に居るんだよー」
ゆーりんが廊下を指差す。
私からは誰の姿も見えなかった。
「その人って、今そこに居るの?」
「今居るんだよー」
私は再び時計に目を向ける。
ホームルームまでは僅か3分だ。
「今って…残り3分しかないよ…?」
「でも、呼んでるんだよー…」
ゆーりんの顔が僅かに曇る。
そんな顔をされたって、時間が無いんだよー。
…いけない、ゆーりんの言葉がうつっちゃった。
「…その人、何の用事か言ってた?」
私は気を取り直して訊いてみる。
「…うーん、分からないよー。ただ“七海理沙さんを呼んで欲しい”って…」
首をかしげながら、ゆーりん。
ちなみに七海理沙(ななみりさ)とは正真正銘の私の名前である。
少なくとも、私に用事があるような人は全く思い浮かばないんだけど…。
「…まあ、そこに居るんならさっさと行って確かめてみましょうか」
悩んでいても仕方がない。
私は自分の中でこう結論を出して立ち上がった。
ガタ。ポス。
私が扉を開くと二種類の音。
最初のひとつは立て付けの悪い扉が開いた音で、次の音は何かが私の頭に降って来て当たった音だ。
頭に当たって廊下側に転がったそれは、どこの学校にでもある黒板消し。
つまり、扉の上に黒板消しを挟んでおいて、頭に当てるイタズラに私は引っかかったらしい。
……なんだってのよ。
「ハーーッハッハッ! 引っかかったな七海理沙!!」
人のいない廊下に声が響く。
見ると、男子生徒がビシッと人差し指を私に向けて高笑いをしていた。
「クハハハハ! 哀れな貴様をさらに絶望へと叩き込む宣言をしてやろう。貴様は俺様の生贄に選ばれた! これから貴様はこの世の中に存在するありとあらゆる苦痛と絶望を味わう事になる! そして貴様は悲しみの涙を流しながら俺様に許しを乞う事になるのだ!」
などとキテレツな事を言っている男子生徒。ボサボサと言うよりツンツンとしたヘアスタイルに見事なツリ目。言動と見かけは迫力がありそうなものだけど……。
先ず、背が低い。私だってゆーりんよりは高いけどせいぜい女の子の平均身長くらいのものだ。その私よりも頭二つ分は低い。そして声。高い。少なくとも同年代の男子よりはずっと高いと思う。
結論……コイツはガキね。
「おおおっ、なんと恐ろしい! この俺様のようなエリート悪魔に目をつけられるとはなんたる悲運、なんたる悲劇! 例えて言うのなら満員電車の中で靴紐を結びなおそうとして屈んだら女のケツに頭から突っ込んで痴漢と間違われる程の悲劇!」
なによ、その例えは。それは自業自得でしょ。……って、エリート悪魔? そういえばさっきからちびっこの男子生徒……自称悪魔の背後でピコピコとアニメにでも出てきそうな悪魔っぽい尻尾が揺れてるわね。
コスプレかなんかかと思ったら、そっか、本物の悪魔だったのか。
……なんで信じるかな、私は。
誰も突っ込んでくれないので自分で突っ込みをいれる私。
「悪魔に目をつけられた人間の末路は全て悲劇でおわりゅにょにゃあ」
「…………」
「…………」
早口で言い過ぎてかんだらしい。
「……つっ、つまりだな!」
「おわりゅにょにゃあ」
「…………俺様が言いたいのはだな!」
「おわりゅにょにゃあ」
「…………」
「…………」
自称悪魔はプルプルと身体を震わせている。しかも涙目だった。
なんだか可愛らしい悪魔ね。ちびっこだし。
「悪魔に目をつけられた人間の末路は全て悲劇で終わるのだ!!」
言い直した。意味無いでしょ、それは。そう思うのだけど、自称悪魔君は満足げに胸をそらせている。うむうむ、と頷きつつ再び人差し指を私に向けて、
「寛大な俺様は貴様がこれから取るべき行動に選択肢を用意してやろう! 選択肢A、俺様に泣きながら侘びを入れて心の底から屈服する事。そして選択肢B、無駄な抵抗をした挙句さらに酷い目にあって俺様に泣きながら詫びを入れる事、だ!」
なんだか良く分からない事を言い出した。いやまあ、最初から訳の分からない事を言ってたけどね。
「さあさあ、選ぶがいい!」
良く考えたら、なんで私こんなのに付き合ってるんだろう。そろそろホームルームも始まるのに。そう言えば先生遅いわね、なんて事を考えたら私の選ぶべき選択肢が見えてくる。
「人間ごとき矮小な存在に対しても寛大な心を持って接する俺様の器の大きさに恐れ入ったら答えはひとちゅにゃにょにゃっ」
「…………」
「………………」
まあ、良いけどね。
「Cね」
「は?」
「答えは選択肢C、教室に戻って寝る、よ」
言って私は教室に戻る。
「まっ、待て待て待て待て! その選択肢は愚か者のえらびゅもにょっ」
自称悪魔君が何か言ってるけど、気にしない。悪魔君とじゃれあうくらいなら睡魔ちゃんとお付き合いした方がマシってものだわ。
自称悪魔君は教室の中にまでは入ってこなかった。
/
ホームルームを終え、ゆーりんと二人で廊下を歩く。
初日から授業があるわけじゃないから、部活動以外の今日の学校行事は全て終わりとなっている。ちなみに、私は部活動無所属で、ゆーりんはなんと文芸同好会と演劇部を兼任してたりする。
もっとも、運動部のように毎日練習漬けではなく、演劇部は文化祭の時やなんかに脚本を書くのを頼まれたりする程度、文芸同好会にいたっては一ヶ月に一回の定期集会があるだけで、その他は自由参加なんだそうだ。
「そう言えば、桜が見ごろらしいわね」
「へー、そうなんだー」
私の横……半歩後ろでぽやーんと応えるゆーりん。
私達が目指しているのは渡り廊下の途中に設置してあるジュースの自動販売機だ。
「市民公園の桜も綺麗に咲いてるらしいわよ」
「へー、そうなんだー」
「花見客で賑わってるらしいわね」
「そうなんだー」
…………まあ、ゆーりん相手に普通の会話の流れを期待してはいけない。ひとつ息をついて続ける。
「実は、今日告白されたの」
「え、そうなんだー」
「…………冗談よ」
「そっかー」
にこにこ、と笑顔を私に向けるゆーりん。そう、聞いて無いわけじゃないのよね。ただ、なんと言うべきか、ちょーっとニブイだけで……。
「次の休み……明後日の日曜日にでも、一緒にお花見に行かない?」
結局、間違えようの無い直球を投げる事にした。
一瞬きょとんとした表情になるゆーりんだけど、すぐに満面の笑みでぽんっと両手をあわせる。
「うんー、理沙ちゃんが誘ってくれると思って、新しいレジャーシートとお弁当箱を買ったんだよー。お弁当はわたしに任せてほしいなー」
……そ、そこまでやってるのならもうちょっと早くに気づいてくれても良いのに、と思ってしまうのは贅沢ってものかしら。
「そう、じゃあ任せるわね。それと待ち合わせの時間と場所だけど……」
細かい打ち合わせをしていると右手に目的の自動販売機が見えてくる。
校舎と体育館をつなぐ渡り廊下の真ん中あたりに、ベンチがふたつと自動販売機がみっつ設置されている。紙コップが出てくるタイプ、紙パックのジュースが品揃えされているタイプ。最後のひとつが定番の缶ジュースの自動販売機で、私が飲むのはいつも缶紅茶と相場が決まっていたりする。女の子らしくないと良く言われる私だけど、これで案外一途なのだ。ゆーりんは牛乳を買ったりスポーツドリンクを買ったりと意外と移り気なのよね。
いつもの様に自動販売機に小銭を入れて缶紅茶のボタンを押し、ガコンという音を確認して取り出し口に手を入れて……缶紅茶が出てきていない事に気づいた。
「なっ、なんでよ!」
あわてて複数ある取り出し口を全部確認するけど、そのどれにも私の百二十円と釣り合う物の存在は無い。ついでに金額表示を見ても当然のように点灯していなかった。
「理沙ちゃんどうしたのー?」
となりの紙コップ自動販売機の前で唇の端に人差し指をあてて、うーん、とどれを買うか悩んでいたゆーりんが不思議そうな顔で問いかける。
こっ、この悔しさと悲しさをどうやって伝えれば良いのよ!
「ハーーッハッハッハッ! かかったな七海理沙!」
いつの間にそこにいたのか、自動販売機の上で仁王立ちして私を見下ろしていたのは朝出会った自称悪魔君だった。
「ククククク。どうだ、俺様の力思い知ったか!」
…………へぇ。
ひらりと自動販売機から飛び降りて、ビシイ! と私を指差して続ける。
「思い知ったらとっとと俺様に屈服するのだ!」
くらえデコピン。
「にょわっ。き、貴様なにを……」
えいえいえいっ。
「にょわっ、くわっ、ひょあっ」
止めに脳天チョップを食らわせようとしたところで距離を取られてしまった。
「なんなのよ、まったく。黒板消しの次は自動販売機に細工? 悪魔も案外セコイのね」
悪魔と言ったらもっとこうスケールの大きい悪行を想像してしまうものだけど、コイツに関してはやってる事が子供のいたずらと大差ないと思う。私にとっては良い迷惑ね。
「そっかー、ジュースが出てこなかったんだねー」
「……そうよ」
ものの見事にタイミングの外れたゆーりん台詞。
「ククク、そんな強がりを言っても無駄だ!」
「強がりじゃないわよ、こんなのただのイタズラじゃない」
「じゃあー、わたしも紅茶を買ってみるよー」
「イタズラじゃない! 悪魔の力を見くびるな」
「見くびるわ」
「えっとー、お金を入れてー、えい」
「泣かす、泣かす、泣かす泣かす泣かす!!」
「泣かしてみせなさいよ。ほらほら」
「あれー?」
「言ったな、メス人間ごときが!」
「言ったわよ、悪魔のガキンチョ!」
「紅茶が二本出てきたよー」
「そんなバカなっ」
「えっ、ホント?」
私としたことが、思わず乗せられてちょーっとだけ熱くなっちゃったみたい。
ゆーりんが両手に一本ずつ紅茶を持ってほにゃりと微笑む。
「ありがとっ、ゆーりん愛してるよっ」
「うんー、私も理沙ちゃんの事大好きだよー」
缶紅茶を受け取る。ひんやりとした感触が掌を刺激した。
「それでー、この人、朝の人だよねー?」
プルタブを起こしながらゆーりんの視線の先を辿ると、顔を真っ白にして口と目を大きく開けた悪魔が彫刻みたいに固まっていた。
缶紅茶が二つ出てきたのが余程ショックだったんだろうか。
「さっき言ってた理沙ちゃんに告白してきた人?」
「……違うわ、それにそれは冗談だって言ったでしょ?」
「あれー、そうだったっけー?」
「そうよ。コイツは……そうね、自称悪魔の少年よ」
「悪魔?」
「そう、悪魔なんだってさ」
「へー、そうなんだぁ」
ゆーりんは疑う素振りすら見せずに納得してしまった。ま、まあこういう娘だしね。
「きっ、貴様何者だ!!」
硬直状態から脱した悪魔がゆーりんをびしっと指差す。今度は顔が真っ赤になってる。
「こんにちはー、理沙ちゃんの友達で、野原由利っていいますー」
深々と一礼。きっちり自己紹介をするあたりはさすがゆーりんね。
「何者もなにも、普通の女の子じゃない。何を言ってるんだか」
「七海理沙は頭が悪いから理解できんのだろうが、この女は悪魔である俺様の力をはじき返したんだぞ! 常人であるはずがなかろうが」
む、頭が悪いとはご挨拶ね。あんたにだけは言われたくないわ。
こうやってすぐ熱くなるのは私の悪い癖なんだけど、分かっててもどうにかなるものでもない。自分の性格なんてそう簡単に変えられるものじゃないし、ね。
私が再度反論しようとしたところでゆーりんが口を挟む。
「わたしって、くじ運が良いからー」
「…………」
「…………」
納得するところじゃないのに、どうしてだか納得してしまうのはゆーりんの人徳かしらね。
ずれたゆーりんの言葉に慣れてる私と違って、再び硬直してしまった悪魔。
「悪魔さんは、理沙ちゃんのお友達なんですかー?」
なっ、なんて事を言うのよゆーりん! 今までのやりとりの何処を見たら友達に見えるの?
「違うわ」
「あれー? じゃあさっき言ってた理沙ちゃんに告白してきた人?」
「もっと違うわ。あれは冗談だって言ったでしょ」
「あれ、そうだったっけ?」
そうよ。
って、良く考えたらなんで私がこんな悪魔に目をつけられてイタズラされなくちゃいけないんだろう。別に信心深い方ではないけれど、悪魔に目をつけられる程に日ごろの行いが悪い訳ではない……と思う。
「おい、悪魔」
「なんだ、七海理沙」
「なんで私にちょっかい出すのよ? 良く考えたらあんたに恨まれるような覚えは無いんだけど」
「ち、気づいたか……仕方が無い教えてやろう。昇級試験だよ」
なにやら聞きなれた言葉が出てくる。
「試験? 試験ってなによ」
「うむ、俺様は今のところC級悪魔なんだが、試験に合格することでB級悪魔に昇格できる仕組みでな……」
「なんでその試験と私にちょっかい出す事が結びつくのよ」
「ここまで言っても分からんのか、やはり頭が悪いな七海理沙。つまり試験内容が無作為に選ばれた人間を不幸にする事なのだ。そしてお前は俺様の栄達の礎となるべく選ばれたと言う訳だ。光栄に思え」
「ちょっとちょっと、何勝手な事を言ってるのよ!」
C級だかB級だか知らないけれど、そんな馬鹿馬鹿しい試験になんで私が付き合わなくちゃいけないのよ。
悔しいのでデコピンをお見舞いする。びし。
「ぐあ」
びし、びし、びし。
「ええい、鬱陶しい!」
それは私の台詞だ、バカ悪魔。
「ふん、どう足掻いたところで貴様に拒否権など存在しない! あるのはさっさと屈服するか、無駄な抵抗をしてより悲惨な目にあって屈服するかのどちらかだ」
「どっちもお断りよ」
「くふふふ、人間と言うのは愚かな存在だな。そのように無駄な抵抗をしゅるのだからな」
「…………」
「おっ、俺様は今でこそC級悪魔だがいずれは最上級悪魔になれる器を持った悪魔にゃのりゃぞ!」
「…………」
「…………」
とりあえず、こいつがダメ悪魔だってのは想像がついたわ。
とは言えどうしたものかしら。黙ってイタズラされるがままは論外としても、どうやって私にちょっかいをかけるのを諦めさせるか……。まったく頭にくる。なんで私がこんな事で悩まなくちゃいけないのよ。
私のイライラが頂点に達しそうになったところで、ほやーんとした声が放たれる。
「Cと言えばー」
声の主は言うまでも無くゆーりんだった。
「炭素記号がCなんだよねー」
相変わらず突拍子の無いところに飛ぶゆーりん。私も悪魔も口を出せずにいた。
「炭素と言えば、鉛筆の芯が炭素で出来てたりするんだけど、実はダイヤモンドも炭素で出来てるんだよねー」
右手の人差し指をピンと立てて続ける。
「つまりー、鉛筆の芯のようなありふれたものでも、ダイヤモンドになれる可能性があるって事なんだよー」
「そ、そうなの?」
「そうなんだよー。だから……」
何を思ったかゆーりんはいきなり悪魔の両手をつかんで微笑む。
「CはCでも鉛筆の芯じゃなくて、ダイヤモンドになるように頑張ってねー」
と、励ましの言葉をかけた。
…………。
「ちょ、ちょちょちょちょちょっ、ゆーりんっ!」
「なあにー?」
「良い言葉だとは思うけど応援してどうするのよ、こいつが頑張ったら私が不幸になっちゃうじゃない」
「あれー、そうだっけー?」
ゆーりん……。
「くくくくくっ、お前人間にしてはなかなか見所があるな!」
ゆーりんに両手を握られたままで悪魔が笑う。
つられてゆーりんも笑う。
私は笑える訳ないでしょ。
「そうそう、悪魔さんのお名前はなんて言うのー?」
そんな私をよそに二人はすっかりと打ち解けてしまっている。
「な、名前か? 名前はまだ無いな」
は?
「名前が無いってどういう事よ」
「ふん、力の弱い悪魔にとって相手に名前を知られると言うのは首に縄をつけられるようなものだからな。だからある程度力がつくまでは固体識別のための記号が割り振られるだけで名前が無いのだ」
「そう言えば、物語やなんかでも悪魔さんは名前が無かったりするよねー」
ゆーりんは言うけど、私は言われてもピンとはこなかった。
「って、あんた最初に会ったとき自分のことをエリート悪魔とか言ってたじゃない。見得を張ってただけって事なのね。実際は見習いってところなんでしょ」
図星をつかれたらしく、ぐぬっとうめき声を上げる悪魔。
「でもー、やっぱり悪魔さんよりもちゃんとした名前で呼びたいなー」
「う、うむっ、そうだな、固体識別番号が『C1492』だから、しーいちよんきゅうにーとでも呼ぶが良いぞ」
私から逃げるためゆーりんの台詞に飛びつく悪魔。
誰が呼ぶのよ、そんな長い名前。
「長すぎるわ……」
素直に感想を述べる私につづいて、ぽんっと音が隣から放たれる。ゆーりんがいつものように両手を胸の前で合わせていた。
「じゃあー、アメリカさんって呼んでもいいかなー?」
ゆーりん、それは国名。
「一応聞いておくわ、ゆーりん。なんでアメリカなのよ」
「えっとね、C1492と言えば、1492年にコロンブスさんがアメリカ大陸を発見した年だからだよー」
「……それだけ?」
「そうだよー、Cは本当は西暦じゃなくて世紀っていう意味なんだけどねー」
C1492と聞いてすぐにその思考にたどり着くのはさすがだと思うけど……、むしろその場合コロンブスじゃないのかしら。なんて事を考えてしまうあたり、私も随分ゆーりんに影響されてると思う。
「それにアメリカってなんか格好良いしー」
「ほう、格好良いか」
「うんー、それに響きも強そうでスマートな感じがするよー」
「くくくっ、そうか! それは俺様にぴったりな名前だな。良し、俺様のことは今後あめりかと呼ぶがいいぞ」
こうして悪魔の呼び名が決定した。
メデタシ、メデタシ。
何の解決にもなってない気がするけど。
「あ、そうだー」
瞬間、悪寒が背筋を走る。納豆と牛乳と生肉と生卵をまとめてミキサーにぶち込んで謎のジュースが出来上がっていくのを見ているかのような感覚。
「今度の日曜日に理沙ちゃんと一緒にお花見に行くんだけど、アメリカさんも一緒にどうかなー?」
予感的中。
「ゆーりんっ、それはダメよ。コイツは私を不幸にするためとか言っていろいろ悪戯を仕掛けてくるんだから、誘っちゃダメ」
「えー……」
そ、そんな悲しそうな目をしても駄目なんだから。
「一緒の方がきっと楽しいよー」
ううっ、俯いたって駄目なものは駄目なんだから。
「わたし、理沙ちゃんとアメリカさんと一緒にお花見に行きたいなー」
…………。
「分かったわ。私は構わないわよ……」
「ありがとー、理沙ちゃん大好きだよー」
後はアメリカが断ってくれるのを期待するだけだけど。
「ほう、花見か。七海理沙が行くのなら俺様も行ってやっても良いぞ」
アンタに期待した私が馬鹿だったわ。
「日曜日が楽しみだねー」
「くくくっ、当日が楽しみだな」
私はひとつため息を吐いてぬるくなった缶紅茶をぐびりと一口飲んだ。
/
「雨ね」
『大雨だねー』
お花見当日、空模様はものの見事に大雨だった。もしかしてあの悪魔が嫌がらせで雨でも降らせたんじゃないかと考えたりもしたけど、そこまで大それた事は出来ない気もする。
「残念だけど今日は中止ね」
『えー……』
電話の向こうからゆーりんのしおれた声が聞こえる。
「私だって残念だけど、この大雨じゃ無理でしょ」
『んー』
こうして電話で話している間にも、もう片方の耳に雨が屋根を叩く音と風が窓を揺らす音が聞こえてくる。さすがにこんな日に外に出る気はしない。
『でもー、アメリカさんに連絡がつかないんだよー』
「アイツの電話番号……知るわけも無いか」
電話番号どころか何処に住んでいるのかも知らない。悪魔が電話をしている姿を想像して、そのあまりのシュールさに思わず苦笑いをしそうになってしまう。
『うんー、だからやっぱり待ち合わせ場所には行ってみるよー』
「ちょ、こんな大雨なんだから待ってるはずがないわよ。危ないし止めときなさい」
『でも、待ってたら大変なんだよー』
ああ、電話の向こうでしおれてるゆーりんの姿が想像できるわ。そんな声を出されたって大雨なんだよー。
「……分かったわ。私も今から行くから」
『うんっ、じゃあ公園前でー』
きっと、ゆーりんは私がこう言うって信じてたに違いない。いや、信じてたと言うより知っていたんだと思う。私ってそんなに分かりやすい性格してるのかな。
「くれぐれも気をつけてね」
『うんー、理沙ちゃんもねー』
電話を切ると、すぐに準備を始める。
と、言っても用意するものなんて何も無いんだけどね。
財布をポケットに入れて、玄関に置いてある傘を手に取る。一歩外に出ると雨の音が途端に大きく聞こえて、風に吹かれた雨が横から直撃する。
……これは傘は無理ね。
玄関の扉を閉めて、部屋のクローゼットの中にある合羽を着込む。安物のビニール製ではなく、ゆーりんと一緒に買いに行ったものだ。そういえば買った時に、
「合羽って言うよりレインコートの方が格好良いと思うんだよー」
ってゆーりんが言ってたっけ。この際どっちでも良いけど。
装備完了。
相変わらず雨の勢いは衰えないけれど、今度は歩けないほどじゃ無かった。
とは言え、歩いて気持ちの良い天気じゃない事も確かな事で……。まあ、考えていても仕方が無い。私はひとつ気合をいれて市民公園への道を歩き始めた。
悪魔が馬鹿めと言い、少女は涙を流し、私は悪魔を殴った。
ごいん。
「にょめっ」
「こら、あんた。なに女の子を泣かしてるのよ」
やっとの思いで市民公園にたどり着いた私を待っていたのは、桜の木の下で女の子を泣かしていたアメリカだった。
雨は相変わらずの勢いで降り続けていて地面を叩き、強風が桜を散らしている。
女の子は背の低いアメリカよりもさらに低くてどうみても小学生くらいだろうか、亜麻色の髪の毛が雨にぬれて頬や首筋に張り付いている。木の下で雨宿りしていたとは言え、こんな雨の中にいたのだから当然二人ともずぶ濡れだった。
頭を押さえてぐぎぎと呻いたアメリカが抗議の声を上げる。
「七海理沙か。言っておくがこいつは勝手に泣いてるだけだ。俺様が泣かしたわけじゃない」
「どうだか」
「い、いえっ、本当なんです。勝手に私が泣いてただけで、アメリカさんは関係なくて……」
女の子が涙を拭いながら言う。
「そうなの? 無理しなくて良いのよ? こいつは正真正銘根っからの悪人なんだから」
悪人も変か。悪魔なんだし。
「いえ、本当に。ご心配をおかけしました」
見た目とは裏腹にずいぶんと大人びた言動の女の子。
「どうだ、七海理沙。俺様の言う通りだったろう。さあ、俺様に詫びを入れろ」
「あんたの日ごろの行いのせいでしょうが。でも……まあ疑って悪かったわ。それで、知り合い? あんたの名前知ってるみたいだけど」
「いや、さっき会ったばかりだ」
じゃあアメリカって名乗ったのか。気に入ったのね、その名前……。
「こいつは桜だ」
「はあ、桜っていう名前なのね」
「違うぞ」
はい?
「違うって……、今自分でこの子は桜だって言ったじゃない」
「だからお前は頭が悪いと言われるにょわっ」
言葉の途中でデコピンをお見舞いする。
「あああ、あの! 私、桜なんです」
「それは聞いたわ」
「いえ、あの、ですから、桜なんです」
言って桜の木を指差す女の子。
えーっと、つまり?
「人間にも分かりやすく説明すると、桜の精ってところか」
「…………」
アメリカを見て、女の子を見て、もう一度アメリカを見て、深いため息を吐く。
まあ、そういうものなんでしょ。悪魔がいるくらいだし、妖精がいても不思議じゃないって事にしておこう。
「そう、分かったわ。私は七海理沙って言うの。よろしくね、さくらちゃん」
「はい、七海さんですね、こちらこそよろしくお願いします」
綺麗にお辞儀をするさくらちゃん。……土砂降りの中で自己紹介なんて我ながら滑稽だと思う。まあ、誰に見られてる訳でもないんだけどね
「で、こんな雨の中いったいどうしたのよ?」
「どうしたもこうしたも、俺様を呼んだのはお前たちだろうが」
「そりゃ……、そうだけど。でもこれだけ雨が降ったら普通お花見は中止でしょ?」
私の言葉をフン、と一笑して腕を組むアメリカ。もし私より背が高ければ見下ろす視線を投げかけてたに違いない。
「馬鹿め、約束を破るのは人間だけだ」
一瞬言葉に詰まってしまう。
「嘘で騙したりはするがな!」
一瞬でも納得した私が馬鹿だったわ。
「理沙ちゃーん、アメリカさんー、お待たせー」
背後からゆーりんの声が聞こえて、次いでパシャパシャと足音が聞こえる。
「こんにちはー、良く降るねー」
「こんにちは、そうね、良く降るわね」
「うむ、こんにちは」
そして三人で挨拶。土砂降りの中で挨拶。公園の桜の木の下で挨拶。
その場に現れた瞬間からすっかりゆーりんのペースね。
「やっぱりアメリカさん来てたんだねー」
「ええ、ゆーりんの言う通りだったわ」
「うむ、今日は花見だからな。さあ花見をするぞ」
流れに乗ってなんでもない事のようにアメリカが言った。
まったく、状況を見ない悪魔ね。
「いくらなんでもこの雨じゃお花見は無理よ。今日は中止にしましょう」
「馬鹿を言うな七海理沙。今日花見をすると言ったのはお前たちだろうが」
「それはそうだけど」
「分かったか馬鹿。分かったらさっさと準備をしろ七海理沙」
だっ、黙って聞いていればっ。一体誰のせいでこんな雨の中公園まで来る羽目になったと思ってるのよ。
普段の私なら多分余裕で流せてたはずのアメリカの言葉につい頭が熱くなってしまった。
「馬鹿はアメリカでしょ! 周りを見てみなさいよ、周りを。人っ子一人いないじゃない。こんな中で花見をやろうっていう方が馬鹿なのよ!」
「なっ、七海理沙! 俺しゃみゃの言う事が聞けないと言うにょきゃっ!」
「…………」
「…………」
また噛んでるし。おかげでちょっぴり和んだわ。
「あ、あの……」
それまで黙っていたさくらちゃんがおずおずといった様子で口を挟んできた。
ふと視線を感じて横を見ると、ゆーりんの目が私を見つめていた。
あ、そうか。
「えっと、こちら桜の精さん。私はさくらちゃんって呼んでるわ」
「そうなんだー。わたし、野原由利って言いますー。よろしくねー」
私の説明になんの異論も挟まないで納得してしまった。
それでいいのかと聞きたくもなるけれど、私だって納得してるんだし、まあいいか。
「は、はい。よろしくお願いします」
お互いに頭を下げあって、さくらちゃんが言葉を続ける。
「あの、ごめんなさい、私が悪いんです」
もう一回頭を下げる。
「この雨と風で、多分花が散っちゃいます。そしたらまた来年まで花が咲かないんですよね。そう思ってたら、なんだか寂しくなっちゃって。そんな風に考えた事今までに無かったのに、涙が出てきちゃって」
涙もろいんだろうか、話を続けていくいちにどんどんしおれていく。
「アメリカさんが言ってくれたんです。馬鹿め、俺様はこの程度の風雨など歯牙にもかけずに花見をするぞ、って。泣いている桜なんか見ても嬉しくもなんともないからとっとと泣き止めって。あはは、私、そう言われてもっと泣いちゃったんですけどね」
アメリカはそっぽを向いていた。この反応は……さくらちゃんの言ってる事が本当って事なんでしょうね。
「だから、ごめんなさい。アメリカさんがお花見をしようとしてるのはきっと私のために……」
「バッ、馬鹿め!」
さくらちゃんの言葉を遮るようにアメリカの声が響いた。
「お、俺様が花見をしようとしているのはだなっ、この大雨の中で花見をすればこれは七海理沙にとって不幸に決まっているだろうがだから無理やりにでみょはにゃみをしゃしぇちぇじゃにゃ!!」
もう、グダグダだった。
まったく、これじゃあ私一人が悪者みたいじゃない。
ゆーりんは相変わらずにこにこしていた。
あの顔は「理沙ちゃん、分かってるよー」って言ってる顔だと思う。
「ゆーりん、お弁当とかの準備は出来てる?」
「うんー、こんな事もあろうかと持ってきてるんだよー」
そう言ったゆーりんの手にいつの間にか重箱らしき包みが握られていた。
「ちょっ、何処から取り出したのよそれ。さっきまで持ってなかったじゃない」
「えー、最初から持ってたよー」
この雨の中そんなの大きい荷物を持ってきて、しかも私が気づいていないなんて事があるんだろうか。あるんだろう。事実は小説よりも奇なりってところなのかしら。
「ふう、分かったわ。じゃあ、お花見を始めましょうか」
私が言うと、親友がほんわか笑って、悪魔はけっと悪態を吐いて、桜はびっくりしたような表情になった。
とは言うものの。
雨降りはお花見をやりやすい環境じゃないわけで。
とりあえず、お弁当が濡れないように桜の木の根元あたりに置く。ゆーりんが持ってきたビニールシートを敷こうとしたら、ゆーりんが止めた。曰く、
「桜の根っこにビニールシートを被せると、根の呼吸を妨げるから良くないんだよー」
なんだそうだ。
結局さくらちゃんが、ちょっとくらいなら大丈夫です、と言ったのでシートを敷いて全員が座る。
木の根元にお弁当が詰まった重箱。そして濡れないようにそれを取り囲んで座る四人。
どういう状態かと言うと、四人が四人とも桜の幹に向かって座っているのだ。これじゃあお花見じゃなくて桜とお見合いしてる気分だけど、なるべく濡れないようにするにはこれが一番具合が良いんだから仕方が無い。
ゆーりんとさくらちゃんはそれでも準備をしている間ずーっと楽しそうににこにこと笑っていて、私とアメリカは邪魔者扱いで準備には参加させてもらえなかった。
アメリカと同じ扱いってのは自分でもなんだか複雑な気分ね。
「おおっ」
「うわぁ……」
重箱の蓋が開けられた瞬間、アメリカとさくらちゃんが驚きの声を上げる。
お弁当の中身は、おにぎりや玉子焼きにから揚げといった定番的なものなんだけど、それらが整然と並んでいて、彩りも海苔の黒い色や鮭おにぎりのピンク色、玉子焼きの鮮やかな黄色などが綺麗だ。
漫画的な表現をするなら、蓋を開けた瞬間にピカー! って光があふれ出したってところね。すごいでしょ。ゆーりんの料理の腕は大したもので、時々お弁当を作ってもらう程なのだ。
……すごいのは私じゃなくてゆーりんだっていう突っ込みは禁止。私だってそのくらいは分かっている。私にはこういう女の子らしい趣味は似合ってないし、これは親友を誇らしげに思う気持ちってやつよね。
「どうぞー」
ゆーりんがふたりに箸を渡すと、アメリカは箸を使わずにおにぎりに手を伸ばしてかぶりついている。
さくらちゃんは箸を持ったまま動かないけれど、遠慮してるんじゃなくてどれから箸をつけるか迷ってる様子だった。
悪魔や桜の木も箸を使うのかしらなどと考えていると、すっと目の前に玉子焼きが運ばれてきた。
「理沙ちゃん、はい、あーん」
「ん」
差し出された箸から玉子焼きをぱくりと口の中に放り込むと、しっとりとした卵の甘みが口の中に広がる。この甘みは蜂蜜ね。子供っぽいと言うなかれ、玉子焼きは砂糖よりも蜂蜜入りの方がずっと優しい甘みがして美味しいのだ。
「ん、おいし」
「良かったー」
こうやってゆーりんの箸から最初の一口を食べるのは私とゆーりんの約束事みたいになっている。
いつからだったかもう記憶に無いけれど、どこで覚えてきたのかゆーりんが「あーん」をやってみたいって言い出したのが始まりだったように思う。
それからずっと続いていた習慣だったけど、学校の教室やなんかでやられるとさすがに恥ずかしい。私がそう言ってその習慣を止めようって言い出したのが、私とゆーりんにとって数少ない……と言うより唯一の大喧嘩の原因だったりする。
結局最初の一口だけというところで落ち着いたわけだけど……、
「はい」
考え事をしていたら今度はから揚げが姿を現す。
ゆーりんは相変わらずにこにこしていたけど、いつもの笑顔を100としたら今の笑顔は75くらいかしら。他の人から見たら同じ笑顔で、もしかしたら私の思い違いかもしれないけど、私はそう思ったのだ。
ま、たまには、ね……。
ぱくり。
一瞬の間。
「えへへー」
うん、120点。
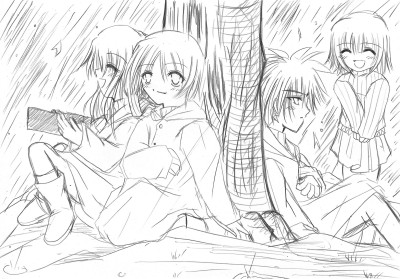
特に特別な事をしたわけじゃない。
おしゃべりをして――。
「さくらちゃんって普段どうしてるの? 今日初めて見たんだけど」
「いえ、普段からいつも公園にいますよ。別に花が咲いていないと存在できないとか、公園から移動できないって訳ではないんです。ただ人間の方は認識できない事が多いですけど」
「へー、そうなんだー。随分イメージと違うんだねー」
「じゃあなんでまた今日に限って」
「俺様の影響だな。そのうち悪霊も寄って来るようになるぞ」
「……勘弁してよ」
騒いで――。
「悪魔の昇級試験には試験期間はないのー?」
「そんなものは無いな。七海理沙が不幸になるか、俺様が諦めるまでのどちらかだ」
「そうなんですか、ちょっと楽しそうです。桜の木には試験はありませんから」
「私は全然楽しくないわ」
「ご、ごめんなさい」
「良いのよ、悪いのはアメリカなんだから」
「分かったら七海理沙、とっとと俺様に屈服せんか!」
「アメリカに素敵な選択肢を用意してあげたわ。選択肢A、さっさと諦めて他の候補を探す。選択肢B、諦めずに私にちょっかいを出し続けて結局試験に失敗する」
「ふん、下らんな」
「ちなみにAは頭の良いヤツが選んで、Bは頭の悪いヤツが選ぶ選択肢ってところね」
「俺様が選ぶのはC、七海理沙の傍にいて不幸にする事、だ!」
「……それは大馬鹿の選ぶ選択肢だわ」
「えへへー」
「ゆーりん、なんで笑ってるのよ」
「ううん、理沙ちゃん楽しそうだなーって思ってー」
「はい、お二人ともとっても楽しそうです」
「…………」
「…………」
皆で笑いあって――。
「アメリカさん、本当にありがとうございます。アメリカさんのおかげで私とっても楽しいです」
「ばばばばばっ、馬鹿な事を言うにゃにょ! 俺しゃまは七海理沙を不幸にする為に花見をやらせようとしただけだ!」
「でもー、わたしも楽しいよー?」
「け、偽善的な悪魔なんてみっともなさすぎるだろうが」
「だとしたら、やっぱりアメリカは悪魔としては二流ね」
「負け惜しみはみっともないぞ、七海理沙」
「負け惜しみじゃないわよ。だって……私も楽しいもの」
「………………俺様も楽しいから引き分けだ」
桜と親友が笑って、私も笑って、悪魔がそっぽを向くような。
そんな、大雨が降りしきる中って事以外にはなんの変哲も無い、何処にでもあるような。
楽しいお花見だった。
/
窓の外の黄色い陽光が西に傾き始めている。
放課後。
私は戦っていた。
何度やっつけても諦める事無く私に挑みかかってくるこの強敵。
あんたも諦めが悪いわね……。
睡魔ちゃん。
放課後なのだ。
帰宅部の私はもう帰るだけなのに、椅子とお尻がくっついたみたいに離れない。
宿題も無い、今日は帰って何かをする予定も無い、何処かに出かける予定も無い。
と、言う事は。
このまま眠っても良いって事ね。
OK、睡魔ちゃん。今日はあなたの勝ちにしておいてあげる。
机の上に投げ出された両腕におでこが近づいていく。視界が黒く染まって……。
「理沙ちゃんー」
援軍が来たみたい。
油断したわね睡魔ちゃん。
「んー?」
目の前の気配に頭を上げず、でろーんとした声で応じる私。
「理沙ちゃん、こんなところで眠っちゃ駄目だよー」
「良いじゃない。寝る子は育つって言うし……、あと五分……」
「五分だけだよー」
………………
…………
……
目の前の気配は動かない。
私を連れ去ろうとしていた睡魔ちゃんはすでに何処かに消えていた。
このまま五分経つのを待つっていうのも面白いかな。面白いかな?
………むくり。
「あれー? 理沙ちゃん、まだ二分十七秒だよー」
腕時計とにらめっこをしてたゆーりんが目を丸くして言う。
予想通りの光景だった。
「ん、目が覚めたわ」
「そっかー」
ぐいっと大きく伸びをすると、例によって肩の骨がバキバキと音を立てる。ゆーりんがしょんぼりした表情を見せるから、どうも最近やりづらい気分になったりもするのだけど、今のところ止めるまでには至っていない。
「それで、今日はなに? 今度は廊下で天使でも待ってるの?」
私が言うとゆーりんがぽんっと両手を胸の前で合わせる。
「あれー、なんで分かったの?」
「そうなのっ?」
悪魔の次は天使? 一瞬目の前が反転しそうになった。
「うんー、さくらちゃんが来てるの。理沙ちゃんに用事があるんだってー」
なんだ、さくらちゃんか……。
「って、待ってるの!?」
「うんー、待ってるよー」
「それなら何で起こさないのよ」
「起こしたけど、理沙ちゃんがあと五分って言ったんだよー」
眉が八の字になる。……私が悪いんだろうか。
「と、とにかくそれなら早く行かないと」
カバンは後でも良いわね。とりあえず廊下に行かないと。
早足で歩き出した私の後にゆーりんが続く。
ガタ。ポス。
扉を開けると音が二つ。
ひとつは立て付けの悪い扉を開いた音で、もうひとつは黒板消しが私の頭に着地した音。
目の前には引きつった苦笑いを浮かべたさくらちゃん。私の頭には白い座布団を敷いて正座している黒板消し。
「どういうことかしら」
「こ、これには深い、そう、ふかーい事情がありましてですね……」
頭の上の黒板消しを右手でひっ捕まえてじりじりとさくらちゃんとの距離を縮める。
「さくらちゃん……お姉さんはさくらちゃんがこんないけない事をする娘だとは思わなかったわ」
「七海さん、おち、落ち着いてくださいっ。ほら、ヒッヒッフー、ヒッヒッフー」
ホホホ、さくらさん、私は十分落ち着いていますわ。
「ハーッハッハッ! 引っかかったな、七海理ひでぶっ」
だからいきなり現れたアメリカに黒板消しを投げつける事だって出来るのだ。
ちなみに顔面にクリーンヒットした。
「よし、今のうちに逃げるわよ」
目の前のさくらちゃんと背後のゆーりんの手をとって走り出す。
「わわっ」
「こんな事もあろうかと理沙ちゃんのカバンもばっちり持ってるんだよー」
さあ、何処に逃げようかしら。喫茶店、カラオケ、ボウリング、きっと何処に逃げたって同じ結末。
「ま、待ちやがれ七海理沙ー! 絶対に不幸にしてやるー!!」
後ろから悪魔の声が聞こえてくる。
全力で走りながら、私はその声に返事をした。
「あんたには無理よー!!」